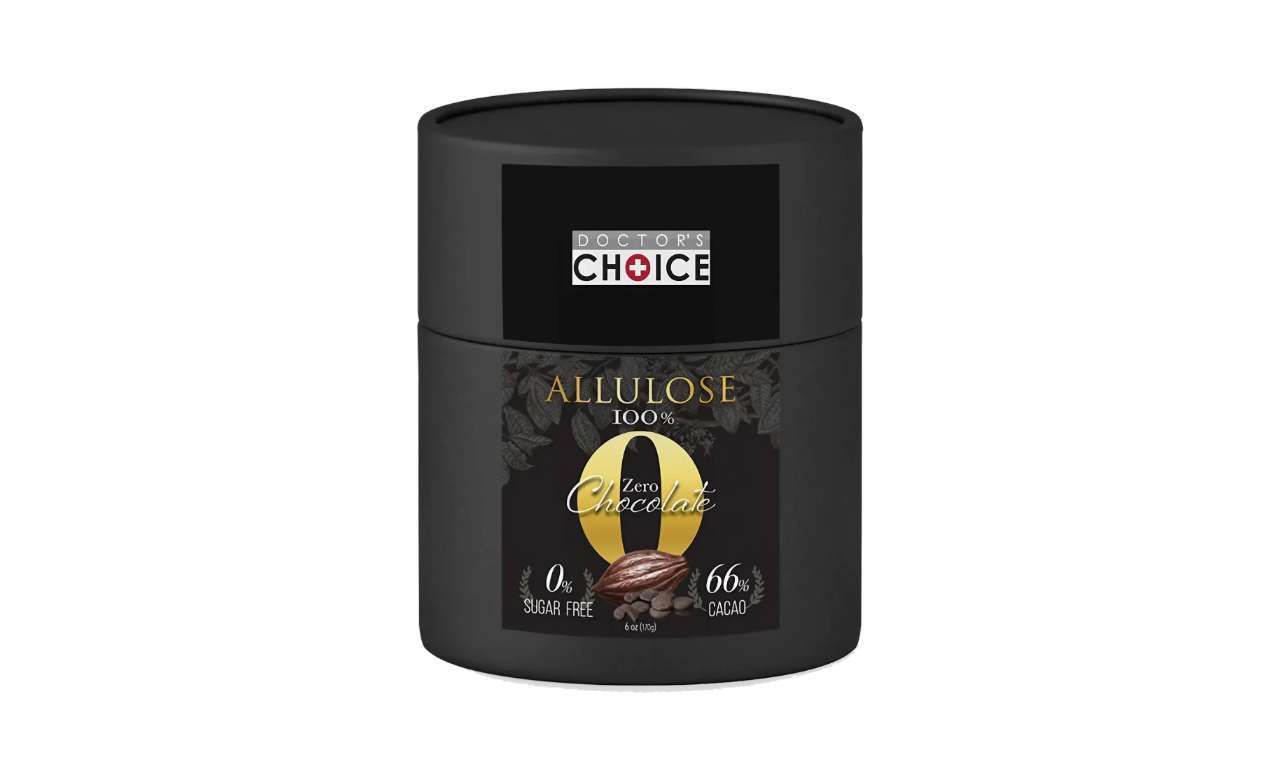近年、健康志向の高まりとともに注目されている甘味料「ステビア」ですが、その一方で「ステビア 発がん性」というキーワードで検索される方も増えています。
人工甘味料に対する不安や、「ステビアは身体に悪いのでは?」「ステビアに危険性はあるのか?」といった声があるのも事実です。
過去には、「ステビアがアメリカで禁止されたことがある」「ステビアは腎臓や不妊に影響するのでは」といった噂が拡がり、それにより不安を感じる方も多かったのではないでしょうか。
血糖値が上がる、太るといった疑問や、「ステビアはスクラロースより安全なのか?」「ステビアは人工甘味料ではないのか?」という疑問も見受けられます。
この記事では、ステビアの発がん性や毒性に関する主要な研究結果を紹介しつつ、日本やEUをはじめとする各国の安全性評価や使用状況、そして一番安全な甘味料とは何かという視点も交えてわかりやすく解説していきます。
信頼できる情報をもとに、ステビアの本当の姿を理解し、不安や誤解を解消する一助となれば幸いです。
- ステビアに発がん性がないとされる科学的根拠がわかる
- 過去の禁止事例や誤解の背景が理解できる
- 国際機関や各国の安全性評価の内容が把握できる
- 腎臓や不妊など健康への影響が事実に基づいて確認できる
ステビアの発がん性の誤解と安全性
- ステビアは身体に悪い?
- ステビアの発がん性に関する主要な研究結果
- 抽出物に発がん性はあるのか
- 甘味料の安全性の根拠とは
- ステビアは人工甘味料ではない
- アメリカで禁止された経緯と現在
ステビアは身体に悪い?

ステビアは一部で「身体に悪いのではないか」と心配されることがありますが、基本的に安全性の高い甘味料です。
食品に使用されている精製されたステビア抽出物は、世界各国の食品安全機関によってその使用が認められています。
なぜ「身体に悪い」と言われるようになったのかというと、過去に動物実験で高濃度のステビアを投与した際に、一部で生殖機能に影響を及ぼしたという報告があったことが背景にあります。
しかし、それは日常的に摂取する量をはるかに超えた過剰摂取によるものです。実際に人間が通常の食生活の中でステビアを摂取した場合に健康被害が起きたという信頼性の高いデータは存在していません。
現在では、国際的な機関であるFAO(国際連合食糧農業機関)やWHO(世界保健機関)も、ステビアの使用を評価し、「ADI(1日許容摂取量)」を設定した上で、安全に使用できるとしています。
日本でも食品添加物として厚生労働省の認可を受けており、多くの加工食品や飲料に使用されています。
通常の摂取量であればステビアが身体に悪影響を及ぼす可能性は極めて低いと言えます。ただし、妊娠中や持病がある場合などは、念のため医師に相談しながら摂取することをおすすめします。
ステビアの発がん性に関する主要な研究結果

ステビアに発がん性があるのではないかという懸念は、一部の消費者の間で長年語られてきました。しかし、実際に行われた科学的な研究の多くは、これとは異なる結果を示しています。
例えば、2021年に発表された包括的な安全性評価では、ステビアに含まれる成分「ステビオール配糖体」が、発がん性の特徴を示す分子的メカニズムを持たないことが確認されました。
この研究では、900以上のメカニズム関連データを評価対象としており、信頼性も高いとされています。
No evidence of carcinogenicity was observed in the 900+ mechanistic data evaluated for steviol glycosides.
引用:ScienceDirect – Evaluation of Steviol Glycosides
国際機関でもステビアの安全性が認められています。
2008年、FAO/WHO合同の食品添加物専門家会議(JECFA)は、ステビオール配糖体の許容摂取量を「体重1kgあたり1日0~4mg」と設定しました。これは、通常の食品摂取において問題がないと判断されていることを意味します。
The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA) established an acceptable daily intake (ADI) for steviol glycosides of 0–4 mg/kg body weight/day.
引用:JECFA(FAO/WHO)安全性報告
抽出物に発がん性はあるのか

ステビアの抽出物に関して「発がん性があるのではないか」という疑問を持つ方もいます。
しかし、これまでの複数の研究において、ステビア由来の抽出物に発がん性が認められたケースは確認されていません。
ステビアには主に「ステビオシド」や「レバウディオシドA」などの甘味成分が含まれており、これらを抽出して製品化されたものが一般的なステビア甘味料です。
科学的な安全性評価を行っている国際的な機関であるJECFA(FAO/WHO合同食品添加物専門委員会)は、これらの抽出物について発がん性や遺伝毒性が見られないことを報告しています。
欧州食品安全機関(EFSA)やアメリカ食品医薬品局(FDA)でも、ステビア抽出物に対する評価は同様で、いずれも「安全である」との見解を示しています。
日本国内でも独自の評価を経たうえで、食品添加物として認可されています。
ただ単に「植物由来の成分だから安全」と考えるのではなく、抽出方法や成分の精製レベル、使用量の管理といった複数の要素が安全性に関わっています。
現在市場で流通しているステビア製品は、いずれもこうした基準をクリアしているものがほとんどです。
したがって、信頼できる製品を適切に使用する限り、ステビア抽出物に発がん性の懸念はありません。
甘味料の安全性の根拠とは
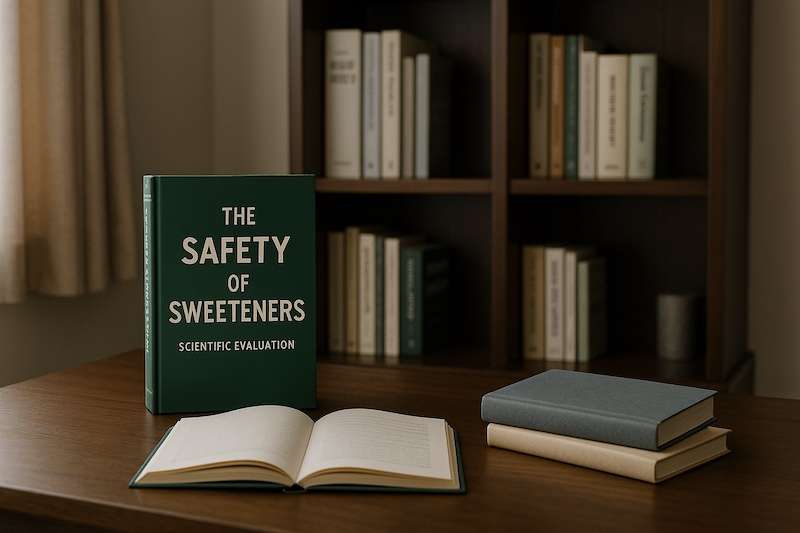
甘味料の安全性は、単に「天然だから安全」「人工だから危険」といった印象で判断されるものではありません。
国際的な安全性の評価基準に基づいた厳密な試験と審査を経て、各国で認可されているかどうかが重要な判断基準になります。
例えば、ステビアを含む多くの甘味料は、動物試験・毒性評価・代謝経路の分析などを通じて、その安全性が科学的に検証されています。
これらのデータをもとに、JECFAやEFSA、FDAといった機関が摂取の安全範囲を設定します。
このときに決定される「ADI(Acceptable Daily Intake=1日あたりの許容摂取量)」は、動物実験で影響が出なかった量をさらに100分の1などに厳しく引き下げた数値です。
各国の法律に基づいて、製品化された際の含有量や使用方法も管理されます。こうしたプロセスを経て市場に流通している甘味料は、過剰に摂取しない限り、健康に対して有害な影響を及ぼすことはないとされています。
もちろん、全ての人に完全に無害というわけではなく、アレルギーや個人差による反応が起きることもゼロではありません。
しかし、それはどんな食品にも言えることであり、正しく知識を持って適切に摂取することが大切です。
このような科学的根拠と国際的評価体制によって、甘味料の安全性は維持されているのです。
ステビアは人工甘味料ではない

ステビアは「人工甘味料」と混同されがちですが、正確には「天然由来の甘味料」に分類されます。
化学的に合成された甘味料ではなく、植物そのもの、あるいは植物から抽出した成分を利用している点が特徴です。
具体的には、南米原産の「ステビア・レバウディアナ」という植物の葉から抽出される成分を甘味料として使用しています。
「ステビオシド」や「レバウディオシドA」といった化合物が甘味のもととなっており、これらを精製したものが現在市場に出回っているステビア甘味料です。
この過程において化学合成は行われないため、「人工甘味料」とは明確に異なります。
天然由来であるにもかかわらず、カロリーがほとんどなく血糖値に影響を与えにくい点で、健康志向の高い人々から支持されています。
「人工甘味料=身体に悪い」というイメージが一部にあるため、それと混同されることで「ステビアも危険では?」と誤解されることがあるのです。
ステビアは自然由来の素材であるという点からも、使用方法を守れば安全性が高い甘味料であると言えます。
誤った認識に基づいて避けてしまうのではなく、正しい情報に基づいて選ぶことが大切です。
アメリカで禁止された経緯と現在

ステビアはかつてアメリカで一時的に使用が制限されていたことがあります。この背景には、安全性に対する科学的な議論と規制当局の方針が関係しています。
1980年代、アメリカ食品医薬品局(FDA)は、ステビアに関する十分な毒性データが不足していることを理由に、輸入および販売を制限しました。
その当時、一部の研究で高濃度のステビア抽出物が生殖機能に影響を与える可能性があると報告されたことが、慎重な判断を促す一因となったのです。
ステビアは「食品添加物」としての認可を得られず、長らく「ダイエタリーサプリメント」としてしか販売できない状態が続きました。
しかしその後、多くの追加研究が行われ、発がん性や毒性、遺伝的影響についても明確なリスクがないことが確認されていきます。
1999年以降に行われた一連の安全性評価を経て、2008年には「高純度のレバウディオシドA」に限ってFDAがGRAS(一般に安全と認められる)認定を与えたことで、事実上の食品添加物としての使用が可能となりました。
現在では、多くの清涼飲料や低カロリー食品に使われており、アメリカ国内でも一般的な甘味料の一つとして受け入れられています。
このような歴史的な経緯から、過去の「禁止」の情報だけが独り歩きし、今でも不安に思う人がいるのかもしれません。
ステビアが発がん性を不安視される理由
- 危険性とその科学的根拠
- ステビアの禁止国があるのはなぜ?
- ステビアとスクラロース危険性の違い
- 腎臓や不妊への影響は?
- 血糖値が上がる?糖尿病への影響
- ステビアで太るって本当?体重との関係
- 日本やEUなど各国の安全性評価と使用状況
危険性とその科学的根拠

ステビアの危険性については、これまでに多くの議論が行われてきましたが、現在入手可能な科学的データを見る限り、通常の使用において大きなリスクはないとされています。
その評価の中心となるのは、毒性試験・発がん性試験・遺伝毒性試験などの結果です。複数の国際機関、例えばWHOやFAO、欧州食品安全機関(EFSA)やアメリカFDAなども含め、いずれも「高純度ステビア抽出物の通常使用では健康に対する懸念は見られない」との結論を示しています。
これに基づき、ADI(1日許容摂取量)も明確に定められており、それを超えない範囲での使用であれば、安全と判断されています。
ただし、全くリスクがないというわけではありません。例えば、腎疾患を抱えている人や妊娠中の方など、一部の条件下では摂取を控えたほうがよいとされる場合もあります。
製品によっては他の甘味料や添加物と併用されていることがあり、それぞれの成分についても注意が必要です。
安全性はあくまでも「通常の使用範囲」におけるものであることを忘れてはいけません。どれだけ安全なものでも、極端な量を摂取すれば何らかの影響が出る可能性はゼロではないからです。
科学的根拠に基づいた正しい理解と使い方をすれば、ステビアの危険性について過度に心配する必要はないと考えられます。
ステビアの禁止国があるのはなぜ?

ステビアが禁止されている国があることは事実ですが、その背景には「科学的根拠の有無」よりも「安全性に関する情報の蓄積状況」や「国の規制方針の違い」が関係しています。
食品添加物や健康食品に関する法律やガイドラインは国ごとに異なり、それぞれが独自の審査基準を設けているため、一律に使用が認められているわけではないのです。
かつて欧州連合(EU)ではステビアの食品への使用が一時的に禁止されていました。
これは一部の研究で、生殖機能への影響や遺伝毒性の懸念が示されたことがきっかけとなり、慎重な姿勢が取られたためです。
しかし、その後の再評価によって安全性が確認され、現在ではEUでも高純度のステビア抽出物は使用が認可されています。
ステビアが「禁止されているから危険」というわけではなく、各国が持つ評価体制やデータの信頼性によって、使用の可否が判断されているケースが多いのです。
科学的な安全性が確認されていても、政治的判断や文化的背景が影響することもあります。
現時点では、WHOやFAO、そして各国の食品安全当局によって「一定の条件下で安全」とされており、多くの国で広く利用されています。
したがって、一部の国での規制をもって、すぐに危険と結びつけるのは早計と言えるでしょう。
ステビアとスクラロース危険性と違い

ステビアとスクラロースはどちらもカロリーゼロの甘味料として知られていますが、成分の由来や体内での挙動、安全性に関する評価には明確な違いがあります。
これを理解することで、それぞれの甘味料が持つ特性を適切に活用できるようになります。
まず、ステビアは南米原産の植物由来であり、天然甘味料として分類されます。一方、スクラロースは砂糖の分子構造を人工的に変化させて作られた「人工甘味料」に該当します。
体内での吸収についても違いがあります。ステビアは消化吸収されにくく、体内で代謝されることなく排出される傾向があります。
スクラロースは一部が腸から吸収され、肝臓で代謝されることもあるため、長期的な摂取に対して慎重な意見もあります。
動物実験においてスクラロースは腸内細菌への影響や、インスリン反応の変化を指摘する研究がいくつか存在します。
一方のステビアは、血糖値の上昇を抑える働きがあるとの研究結果もあり、糖尿病患者などにとって有用な甘味料とされています。
これらの違いを踏まえると、どちらが「安全」と断言するのではなく、目的や体質、摂取量に応じて使い分けることが望ましいでしょう。
天然由来のものを好む人にはステビアが適しているかもしれませんし、味やコストを優先する場合はスクラロースが選ばれることもあるかもしれません。
腎臓や不妊への影響は?

ステビアの使用が腎臓や生殖機能に影響を与えるのではないか、という不安を持つ人は少なくありません。
これは、過去に動物実験で指摘された一部の結果が広まったことに起因していると考えられます。
腎臓への影響については、一部の研究で高濃度のステビア抽出物をラットに投与した際、腎機能に変化が見られたと報告された例があります。
ただし、これはあくまで通常の食事では考えられないほどの大量投与で得られた結果であり、一般的な摂取量とは大きくかけ離れています。
その後、人間に対するリスク評価を行った複数の国際機関は「通常の範囲であれば腎臓に悪影響を与える証拠はない」としています。
不妊に関しても、同様にラットを用いた動物実験において、一時的な精子数の変動が見られたとする研究がありますが、これも極端な量を長期間にわたって摂取した場合の話です。
人間を対象とした信頼性の高い研究では、ステビアの摂取が生殖機能に悪影響を及ぼすという明確な証拠は見つかっていません。
ただし、妊娠中や腎疾患を抱える方など、体調に特別な配慮が必要な人は、念のため医師に相談した上で利用することが望ましいでしょう。
安全性が確認されているとはいえ、個人の体質や健康状態によって影響が異なる可能性があるためです。
現在の科学的根拠に基づけば、適切な量を守っていればステビアが腎臓や不妊に直接的な悪影響を及ぼすという懸念は小さいと言えます。
過剰に恐れるのではなく、正確な情報に基づいて判断する姿勢が大切です。
血糖値が上がる?糖尿病への影響

ステビアは、血糖値への影響がほとんどないとされており、糖尿病患者や血糖コントロールを気にする人々にとって注目されている甘味料のひとつです。
多くの甘味料は血糖値を急激に上昇させる可能性がありますが、ステビアはその性質が大きく異なります。
ステビアの甘味成分であるステビオール配糖体は、消化管で分解されてもグルコースとして吸収されることがなく、そのまま代謝されずに体外へ排出されるとされています。
つまり、血糖値を上げる作用がほとんど見られないのです。実際、いくつかの臨床試験では、ステビアの摂取が空腹時血糖値やインスリン反応に影響を及ぼさなかったことが確認されています。
糖尿病予備軍の方やインスリン抵抗性を持つ人々に対して、ステビアがインスリン感受性を改善する可能性を示す研究も報告されています。
ただし、すべての研究結果が一致しているわけではなく、体質や食生活によって結果にばらつきが出ることもあります。
「血糖値が上がるのでは?」と不安を抱く人も少なくありません。それは、他の人工甘味料と混同されるケースがあるためです。
例えば、スクラロースやアスパルテームなどの人工甘味料には、腸内環境に影響を与えることで間接的に血糖値に作用する可能性があると指摘されています。
しかし、ステビアはそのような懸念が低く、むしろ腸内細菌に良い影響を与えるという見解もあります。
血糖値の急上昇を抑えたい方にとって、ステビアは比較的安全性が高い選択肢のひとつです。
ただし、すべての人に同じような効果があるとは限らないため、自分の体調や医師の指導に基づいて取り入れることが重要です。
ステビアで太るって本当?体重との関係

「カロリーゼロ」と聞くと、多くの人は体重増加とは無縁のイメージを抱きがちですが、ステビアを使っても太るのではないかという声があるのも事実です。
しかし、実際にはステビア自体が直接的に体重を増やす原因になることはほとんどありません。
ステビアはゼロカロリーでありながら高い甘味度を持つため、砂糖の代わりとして少量で甘さを感じることができます。
摂取カロリーを抑えるという点では、ダイエットや体重管理に有効とされています。
甘いものを我慢せずに楽しめる点で、過剰なストレスを避けながら摂取カロリーをコントロールできるのは大きなメリットです。
それでも「ステビアで太った」と感じる人がいるのはなぜでしょうか。その原因の多くは、ステビアを使用した食品全体の内容や摂取量にあります。
ステビアを使っていても、油分やその他の糖質が多いスイーツや飲料を多量に摂取してしまえば、当然ながら総摂取カロリーが増えて体重増加に繋がる可能性があります。
甘味料によって脳が「糖分を摂取した」と錯覚し、食欲が増すという指摘もあります。
この点については個人差が大きく、科学的にも完全に結論が出ているわけではありませんが、ゼロカロリーに安心しすぎて他の食事量が増えてしまうというのは、どの甘味料にも共通する注意点です。
ステビアは体重管理に役立つ成分ではありますが、使用方法や食生活全体のバランスが重要になります。
むしろ、甘いものを無理に我慢するより、ステビアを上手に活用することで、健康的なライフスタイルを維持しやすくなる可能性があります。
上手な使い方を心がけることが、結果として体重コントロールにもつながるでしょう。
日本やEUなど各国の安全性評価と使用状況

ステビアの利用は世界中で広がっており、安全性に関しては各国の公的機関が評価を行っています。
その中でも、日本と欧州連合(EU)の基準は特に厳しく、それに適合していることは安心材料となるでしょう。
日本においては、厚生労働省によってステビオール配糖体が食品添加物として認可されており、飲料や加工食品などに広く使用されています。
過去には原材料の精製度などが議論の的となりましたが、現在使用されている高純度のステビオール配糖体に関しては、安全性が十分に確認されています。
欧州では欧州食品安全機関(EFSA)がステビオール配糖体に対する厳格な評価を行い、2011年には食品添加物としての使用を認可しました。
現在では、EU全域で使用が可能になっており、多くの製品に導入されています
EFSA has concluded that steviol glycosides are not of concern with respect to genotoxicity and are safe when used in accordance with the proposed uses and use levels.
引用:EFSA Journal – Steviol Glycosides Evaluation
ステビアの発がん性に関する総括と安全性のまとめ
記事のポイントをまとめます。
- ステビアは天然由来の甘味料で人工甘味料ではない
- 通常の摂取量では健康被害の報告は確認されていない
- 国際的な機関がステビアの安全性を評価している
- 発がん性に関する科学的根拠は否定的な結果が多い
- ステビア抽出物は発がん性の懸念がないとされている
- 過去にアメリカで一時的に使用が制限された経緯がある
- 現在ではアメリカでも食品添加物として認可されている
- 高濃度で生殖機能に影響が出た動物実験がある
- EFSAやJECFAはステビアのADIを明確に設定している
- 糖尿病患者でも使用が可能とされ血糖値への影響が小さい
- 一部の国で禁止された理由は科学的根拠よりも政策判断による
- スクラロースとは成分と体内動態に明確な違いがある
- 腎臓や不妊への影響は人間では確認されていない
- 体重増加との直接的な関係性は示されていない
- 現在の製品は高純度で安全性が担保されている